音響家技能認定講座開催案内
実施を決定した時点で広報いたしますので、お問い合わせはご容赦ください。
音響家技能認定講座・ビギナーズコース兵庫開催
劇場・ホール等で働くプロの音響技術者の「心構え」と「基本の技能」を実際の劇場で体験しながら習得していただきます。講義終了後に実施する理解度試験で3級音響技術者の資格が得られます。ビギナーはもちろん、経験者のスキルアップ、再確認に受講しておきたいセミナーです。
実施日 2024年9月11日(水)
受講費 受講料:12,100円(会員6,050円)税込み、教科書と検定料含む
※入会と同時に受講申込みいただいた場合、会員扱い料金とさせていただきます。
開場 兵庫県県立芸術文化センター 阪急中ホール
https://www1.gcenter-hyogo.jp/access/
募集人数 20名
申込みフォーム ここをクリック
主催 一般社団法人日本音響家協会
共催 一般社団法人日本音響家協会西日本支部
共催 兵庫県立芸術文化センター
内容
第1章 劇場の仕事
第2章 舞台音響の仕事
第3章 舞台進行の仕事
第4章 舞台照明の仕事
第5章 音響機器の仕込作業
第6章 調整卓の設定
第7章 調整卓の操作
マイクチェック・スピーチのSR・音楽再生と対話のSR
第8章 コミュニケーション
第9章 バラシ(撤収)
ビギナーズコース 洗足学園音楽大学開催
日 時:2024年5月20日(月)10時~18時
会 場:洗足学園音楽大学・前田ホール
主 催:一般社団法人日本音響家協会
協 力:洗足学園音楽大学
ビギナーズコース札幌
日 時:2024年2月28日(水)10時~18時
会 場:札幌サンプラザホール
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:一般社団法人日本音響家協会北海道支部
サウンド システム チューナコース2級 オンライン(Zoom)
日 時:2024年2月6日(火)
本部事務局から発信
サウンドシステムチューナコース2級対象は、次のようなことが理解できます。
音場補正でチューニングして有効なピークまたはディップは次のいずれか?
□複数のスピーカ同士の時間差による位相干渉によるもの
□室内(劇場内)音響特性によるもの
□反射音による位相干渉によるもの
この講座はチューニングソフト操作のセミナーではなく、スピーカの正しい設置方法と音場補正を実施する前に知っておきたい基礎知識について学ぶ内容です。
この講座で、見えていない音が見えてきます。
ビギナーズコース名古屋開催
日 時:2023年12月21日(木)10時~18時
会 場:名古屋市昭和文化小劇場
受講料:12,100 円(SEAS 会員6,050 円)教科書+技能認定経費を含
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:一般社団法人日本音響家協会中部支部
2023年12月21日、名古屋市昭和文化小劇場にて、日本音響家協会主催、音響家技能認定講座ビギナーズコースをおこないました。
劇場に勤務される方、音響メーカーにお勤めの方、イベント業に従事している方、興味があって勉強したい方など様々な方、19名の参加がありました。
テキストにしたがって、劇場の仕事に関する基本的な知識から音響の実践まで様々なことを学びました。参加者の皆様は音響卓を初めて操作する方から、操作はしたことがあるが指導を受けたことがない方など、経験は多種多様な状況でしたが、実践を通し音響についてより深く理解することができました。講座終了後、Web試験に合格された方の18名が、3級音響技術者に認定されました。
報告:大矢英和

クリエイティブコース大阪開催
日 時:6月21日(水)11:00〜17:00
会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:一般社団法人日本音響家協会西日本支部

▲音楽音響機器

▲演劇音響機器
ビギナーズコース洗足学園音楽大学開催 実施報告
日 時:5月8日(月)10時30分開始
会 場:洗足学園音楽大学 前田ホール
協 賛:洗足学園音楽大学 音楽環境創造コース
主 催:一般社団法人日本音響家協会



▲2人の会話をSR実習
筆記試験の2つの設問の解答をまとめました。
舞台のスタッフとしてのコミュニケーションの大切さについて述べよ
●自分の言いたいことを相手に分かりやすく傷つけずに伝えられる力があれば、演者さんや他のスタッフさんと円滑に作業を進めることができます。また、相手側から見て自分が話しかけやすい雰囲気であれば、要望や質問を投げかけやすく満足のいく公演を行える可能性は高まるかもしれません。講座でも仰っていたように、舞台関係の仕事は多くの人と関わる仕事です。先輩方と食事に行った際に、先輩のノウハウや知識を分けていただくことも沢山あります。公演を無事に終わらせるためだけでなく、自身の技術の向上においてもコミュニケーションは欠かせない大切なものです。
●舞台は多くのスタッフのそれぞれの持ち場での働きによって一つの作品がつくりだされます。スタッフには高度なスキルが求められ、作品をいかに最高のものとするため制作者、出演者の意図をくみ取って実行していくかが求められます。そのためには舞台スタッフ同士の連携、何よりも制作者、出演者からの要望を実現していくためにしっかりコミュニケーションをとることは必須といえます。そのようにしてスタッフの黒子としての働きの支えによって出演者が気持ちよく最高のパフォーマンスを発揮できれば、それは観客を喜ばせるという目的を達成できるものとなります。舞台スタッフ同士がしっかり肝に銘じなければならないのは建設的、積極的、お互いへの敬意と感謝、そして安全確認、これをはっきり言葉にすること、これはとても大切です。
●舞台の仕事はコミュニケーション無しには成り立ちません。演出家の意図を汲み取るのにも、出演者との意思の疎通、スタッフ同士の協力においてもコミュニケーションが極めて重要です。
適切なコミュニケーションが図れないと、良い舞台が作れないだけでなく、事故の元にもなります。
●舞台スタッフ同士のコミュニケーションを取ることにより、次に何をするのか?何をしたいのかを相手に巧く伝えることが可能になる。また、コミュニケーションを取ることにより舞台で起きる事故のリスクを減らすことにもつながる。特にミュージシャンとのコミュニケーションは非常に大事であり、意思疎通ができないと良い仕事はできない。
●コミュニケーションをとることは演出の意図を正確に汲み取り高い水準で表現するためには欠かすことができない。また、共に作業するスタッフと声を掛け合うことで互いの安全を守ったりして、スムーズな運営を実現できる。自分の担当以外の人とも積極的に関わることで、深い理解や新しい視点を得ることができる。
●舞台スタッフとしてのコミュニケーションは、現場にいるさまざまな分野のスタッフの意思、感情、思考を共有し、全員が同じ方向に向かって働き、舞台をより良いものにするために必須である。また、先輩や初めて出会った人とコミュニケーションをとることは、新しい知識や学びを得られる機会であるため、自身のスキルアップにも繋がるものである。さらに、コミュニケーション能力を駆使し、さまざまな人と対話し、いろいろなことを学び、想像力を磨くことにより、AI時代にも生き残れる人材になり得る。
●スタッフ同士のコミュニケーション不足による事故や仕込みの遅れなどが起こった場合、演者さんや他セクションのスタッフ、舞台に関わっているすべての人たちに迷惑がかかる。みんなで舞台を作り上げてゆくために、些細なことでも声を掛け合ってコミュニケーションをとることは大切である。
●どんな舞台をつくりたいかなどの意思の疎通や情報共有をスムーズにすることができます。また、日頃から積極的にコミュニケーションをとっておけば、私的な場でもちょっとした技術的な話が聞けるかもしれないなど、自分の技術アップにも繋がると考えられます。
●舞台のスタッフとしてのコミュニケーションは様々な分野の大勢のスタッフと同じ方向を向いて働くために大切だ。そのためには相手の立場や地位を考慮し上手く発現する必要があり、先輩と交流する中で学ぶ必要がある。また、AIと異なり人間にはコミュニケーション能力と想像力がある。今後生き残る人材になるためにも、舞台スタッフはコミュニケーションを大切にしていくべきだ。
●舞台は一人では完成させることができず、みんなで力を合わせて頑張った結果なのです。その間の各パートを担当するスタッフとのコミュニケーションはとても重要です。絶え間ないコミュニケーションがあってこそ、華やかな舞台を観客にお見せすることができるのです。コミュニケーションは、自分が望んでいることを伝える最も簡単で直接的な方法です。スタッフとしては、自分が担当するプロジェクトを成功させることが最終目的ですから、その一環として、コミュニケーションにも非常に重要です。もちろん、キャストやスタッフとのコミュニケーションも不可欠で、みんなで協力してこそ、完璧なものを観客に見せることができるのです。これは舞台のスタッフとしてのコミュニケーションの大切さだと私が思っています。
●コミュニケーションを行うことで、自分の気持ちや考えが相手に伝わると共に、相手の気持ちや考え方も分かるため、お互いの理解を深めることができる。AIにはできない、新しいものを生み出す発想力、想像力を養うにはコミュニケーションをとり、さまざまな人の意見を聞くことで自分の感性が豊かになるため、コミュニケーションは重要であると言える。
●舞台のスタッフとしてのコミュニケーションは、スムーズな舞台運営のために非常に重要です。舞台には多くのスタッフが関わり、演出家、舞台監督、照明技師、音響技師、舞台美術家、俳優、ダンサー、ステージマネージャーなどがいます。それぞれが担当する仕事や役割が異なるため、コミュニケーションがうまくいかないと、誤解やトラブルが生じる可能性があります。スタッフ間でのコミュニケーションは、お互いが意図することを正確に伝えることが必要です。また、コミュニケーションは、スタッフ間の信頼関係を築くためにも重要です。良好なコミュニケーションを通じて、互いに尊重し、協力し合うことができます。
●舞台のスタッフとしてのコミュニケーションの大切さについて述べよ: 舞台をつくっていくうえでコミューケーションとても大切なことである。
舞台スタッフ同士でコミュニケーションをしっかりとることで、効率よく作業を進めることができる。また、作業をしていくうえで声出しなどをすると、事故を減らすことができる。また演者とコミュニケーションをとることで、信頼関係を築くことができ、演者さんが気持ちよく演じることができる。
●大切なのは、自分の言いたいことを相手に巧く伝えることで、相手の立場や地位等も考慮して上手に発言しなければならないのです。そして礼儀と感謝を重んじて、技術スタッフとしてだけでなく、社会人としての作品を充実させる。またミュージシャンとのコミュニケーションはとっても重要です。
●プランをする上では演出家がどのような意図を持って作品を創ろうとしているのかということに応えるため、演出家の想いを汲んでプランをする照明家、舞台美術家らとのコミュニケーションは必須である。仕込みバラシなどの現場では、安全に行うために互いの動きを声かけで知らせたり、それに応えたりするコミュニケーションが必要である。また音響スタッフとして成長するためには先輩とのコミュニケーションが重要だ。先輩がどのように音を聞き、音をつくっているのか、学ぶ機会を逃さないようにして、自分自身の経験に先輩の学びを生かすことで成長することができるからである。舞台では演出家、出演者、照明、舞台美術、大道具、衣装など様々な分野のプロとともに1つの作品を創り上げる。そうした沢山の人々によって支えられていることへの感謝と敬意を行動や言動に表すこともコミュニケーションとして大切であると考える。
この講座で学べたことを述べよ
■今回の講座では、音響の技術よりも大切な、音響家という仕事の楽しさや誇り、目指すべきところを学んだ。印象的なのは、わたしたちの仕事は欲求段階でいう一番上の、「人を楽しませたい、喜ばせたい」という思いが生んだ仕事であり、感動したいと願う人たちへ感動を届けることができる、素晴らしい仕事だというお話である。生物として生きるために必須なものを超えた先の、人間として豊かに生きるために必要なものを提供する仕事ができるのはとても幸せで尊いことだと感じることができた。その想いを持った上で、音響がすべきことは、「心地よい音を届けること」である。何のためにスピーカーを設置するのか、どのように届けたいのかということを考える上で立ち戻るべき指針を学ぶことができた。
■まずは音響家として仕事するときの態度を勉強しました。次に舞台進行、照明、音響の仕事の基本を勉強し、関連する実技もやりました。例えば台組の設置、鉄管結びのやり方などです。そして音響機器の仕込み作業、調整卓の設定と操作も実技で練習しました。私は外国人としてスピーカチェックなどの言い方をすごく勉強になりました。さらにコミュニケーションの重要性を勉強しました。最後はみんなと一緒に機材のバラシをしました。一日中、講座で理論と実技を学んで本当に勉強になりました。
■普段、学校で音響の機材の使い方などを習っているが、大きいホールでの聞こえ方や音楽と声の音量差など初めて知ることが多かったので、とても勉強になった。また、音響以外の照明や舞台の基礎を学ぶことができ、灯体を吊ったり、平台を組んだりなど実践的なこともできたので良かった。
■今回の講座で、舞台装置の名称や、照明器具の取り付け方、大まかな音響の仕込み方を学ぶことができました。音響でも、舞台進行や照明についても理解することで、スムーズに仕込み、バラシを行うことができると感じた。より良い舞台を作るためには、スタッフだけでなく演者とのコミュニケーションも重要であり、舞台に関わる全員が観客を喜ばせるというひとつの目標に向かって足並みを揃えることが舞台成功へ繋がると改めて学ぶことができた。
■今回の講座をとおして、舞台人の大変さを実感しました。
良い舞台の裏には、数え切れないほどのスタッフが、常に裏方として奮闘し、舞台を完成させているのです。だからこそ、すべての舞台スタッフが尊敬されるべきなのです。そして、こうした仕事が自分に回ってきたとき、それをやり遂げるために自分が引き受けなければならない責任感があるのです。舞台は戦場のようなもので、コミュニケーションや技術面だけでなく、何よりも安全面は一番大切です。安全を確保した上で、仕事を完成させることができます。なおかつ、仕事の始まりと終わりにする挨拶とコミュニケーションも不可欠だ。一人で仕事をするより、積極的なコミュニケーションをとり、みんなで仕事を共有して効率的に仕事を進めることができます。“自分の能力をどう活かすのか?” これも自分にとっては今後の課題だと思います。今後も、プロの舞台スタッフになれるように頑張りたいと思います。
■この講座を通して私は以下のことを学ぶことができました。
・舞台での基本
・舞台音響の仕事
・劇場での仕事で意識するべき大切なこと
まず舞台での基本について、日々の業務の中で薄れてしまいがちな心得や毛氈のかけ方や鉄管結びなどを学ぶことができました。この仕事を始めて約半年が経過しましたが、この講座で時間をたっぷり取って改めて基礎を学ぶことができたのは今後の業務をより良くできると感じました。
次に音響についてですが、音響がどのように仕事をしているのか、電源の順番やケーブルの整頓について学ぶことができました。私は主に照明を担当することが多いのですが、音響さんがどんなことを考えているのかが少しでも分かれば同じ方向を向いて仕事をするためにも学べたことは大きかったと感じています。最後にこの仕事で意識するべき大切なことですが、特にコミュニケーションが非常に重要であることを学びました。これは舞台スタッフの仕事にとどまらずどんな仕事にも言えることであり、今後の長い人生の中でずっと意識していく必要があると改めて感じました。以上のことから、この講座では様々なことを学ぶことができました。今後はこれらを活かしてより良い人材になれるよう努めたいと思います。
■この講座に参加してみて、何をしたいのか、何をしてほしいのか、相手の汲み取り能力に頼らずともわかりやすく簡潔に伝えるよう意識する必要があるなと感じました。会話はもちろんですが、身振り手振りもコミュニケーションの一部であり、物理的に距離のある舞台上と調整卓などでは身振り手振りも積極的に使っていくとより効果的だと体感しました。
■お客さん第一なのはもちろん、舞台人としての立ち居振る舞い、幅広く知識を持つこと、スタッフたちとのコミュニケーションの楽しさと大切さ、また初対面の人たちと作業をする際に大切な気遣いを学ぶことができた。
■演劇の演出部として数年関わってきましたが音響に関しては素人で、知識を身に付けたいと思い参加しました。講座の内容としては初歩的な部分や音響家としての心構えから教えていただくことができ、また音響以外のスタッフワークについても理解を深めることができました。今回の講座で得た知識を活かし、今後の仕事の中で実際に再確認しながら理解を深めて行きたいと思います。
■もう一度、基本を学び直す良い経験となりました。特に初対面の学生さんとコミュニケーションを取れたことは滅多にできない良い機会となりました。今後も機会があれば、ぜひ参加したいです。
■学べたことは大きく分けて三つあります。一つ目は、音響、照明、舞台の構造など基礎的な知識が培われました。実際に機材に触ることができたので、頭の中の知識がより鮮明になったと感じます。二つ目は、音響スタッフの舞台人としての心のあり方です。観客を楽しませることや感動させることを目標とし、劇場を支える人々と同じ方向に向かって働くこと、お互いを尊重し合うことも舞台をより良いものにする大切な要素なのだと学びました。三つ目は、コミュニケーションの大切さです。実技をする中で、声かけや身振り手振りによる情報伝達がスムーズな作業進行に繋がると実感しました。また、他の受講生の皆さんと交流をしましたが、たった一日でも多くの学びがありました。普段から相手とコミュニケーションをとることで、相手の思考に一歩近づくことができ、発言しやすい環境を作ったり、理解し尊重したりすることに繋がるのだと感じました。
■自分は普段カメラマンをしておりまして、特に動画撮影の仕事でホールの方々と関わらせていただいており、趣味の楽器関係で演奏会や発表会での舞台や音響スタッフとして動くことが非常に多いため、この講座できちんと学びたいと参加をしました。今回、舞台や照明・音響の基本的なところで、自分がよく分かっていなかったことがとてもクリアになり、本当に勉強になりました。それと、舞台や音響に関わる人の最も大事で基本的な心構えの部分を改めて教えていただきました。AIに関してのお話は音響の仕事に限らず、どの分野の仕事にも通ずることだと思いました。ありがとうございました。
■私の実務経験はボランティアレベルの音響操作とステージ設定ぐらいで、全くの自己流で行っていました。こうした講座があること知り申し込ませていただきました。舞台スタッフとしてのコミュニケーションがいかに大切かを教えていただきました。個人の技術スキルをあげることはもちろん大切ですが、それにもまして舞台作品を作り上げるスタッフ全てが同じ気持ちで一致していなければより良い作品にはならないことをしっかり心に刻みました。受講者同士が初対面でも、スタッフと出演者という両方の立場の実技をとおしてお互い一生懸命参加して「講座」という「一つの舞台」を作りあげることができたのは貴重な学びでした。音響スタッフの仕事は、コンピュータには決してできない人間の感性をフルに発揮できる仕事であることを認識いたしました。
■この講座では多くのことを学んだが、中でも教えていただいた安全を考慮するということが意識できた。普段ステージに立つこともあるが、演奏に集中してしまっており危険な場所にいるということを認識できていなかった。そのため、一つのミスや確認を怠ることによって演奏者やお客様に重症を負わせてしまうかもしれないということを意識したい。また、安全を考慮しないとプロフェッショナルな仕事が台無しになってしまうと感じた。その上で、知識はもちろんだが、考えや発想などで演者さんが気持ちよく演奏できるように、お客様に気持ちよく聞いていただけるように、素晴らしいものをより素晴らしくして届けられるようにしていきたいと感じた。個人的に調整卓の設定は知らないことも多かったため、少しずつ学びを増やしミキシング等でも知識を増やしていきたいと感じた。
■コミュニケーションの大切さはもちろんのこと、普段やる機会がほとんど無い演者さん側に立つことで、音楽や音量感によって会場の雰囲気そのものがなんとなく変わることを肌で経験できました。また、他の分野のスタッフさん方がどんなことをしているのか詳しく知らなかったので、それを学んだ上で一部だけでも実際に行えたことで、他の分野への理解も講座を受ける前より深められたと思います。マイクケーブルのコネクタを差し込むときの向き、マイクスタンドやスピーカースタンドへのケーブルの這わせかた一つとっても知恵と工夫が詰まっており驚きました。実際の公演ではもっと多くの工夫があるのだと思います。その中のほんの少しだけでもこの講座で学べたと思うので、これを参考に自分でももっと工夫していきたいです。
ビギナーズコース兵庫開催 実施報告
開催日:2023年3月3日(金)
開 場:兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:一般社団法人日本音響家協会西日本支部
ビギナーズコース札幌開催 実施報告
開催日:2023年2月15日(水)
会 場:札幌サンプラザホール
北海道では3年ぶりの開催です。
前回は「コロナ渦」が始まる頃でギリギリの開催、そして今回はまもなく「コロナ渦」収束方向の時期です。これからは通常の周期で開催できればと思います。
この講座で最も大切にしている最後の講義「コミュニケーション」を、きちんとして熱心に受講いただきました。そのような姿から、この講座の必要性を改めて認識しています。 【坪田栄蔵】



ベーシックコース・オンライン開催 実施報告
講義はZoomによる配信、筆記試験はオンラインで実施し、成功裏に終了しました。
開催日:2023年2月13日(月)〜14日(火)
発信会場:東京・調布市 FUSHA tea lounge

ビギナーズコース名古屋 実施報告
日時:2022年11月30日(水)10時30分~17時30分
場所:名古屋市 昭和文化小劇場 ホール
講師:犬塚 裕道 大矢 英和 丹羽 功 松島 大樹
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:一般社団法人日本音響家協会中部支部


クリエイティブコース富山 実施報告
インストラクタ:新谷美樹夫(ジャズ)、糸日谷智孝(演劇)
日 時:2022年7月12日(火)11時〜17時
会 場:富山県・高岡市生涯学習センター4F ホール&406スタジオ
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:一般社団法人日本音響家協会北陸支部
後 援:富山県公立文化施設協議会、福井県公立文化施設連絡協議会


ビギナーズコース特別編 実施報告
日時:2022年5月23日(月)
会場:洗足学園音楽大学 前田ホール
受講対象:洗足学園音楽大学学生
協力:洗足学園音楽大学

▲前田ホール(洗足学園音楽大学ホームページ引用)

▲灯体の吊り込み作業実習

▲台組の作業実習
ビギナーズコース兵庫 実施報告
開催日:2022年3月7日
会場:兵庫県立芸術文化センター
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:兵庫県立芸術文化センター
共催/主管:日本音響家協会西日本支部
後援: 全国公立文化施設協会近畿支部
以下は筆記試験の解答です。匿名で掲載させていただきます。
Q 舞台のスタッフとしてのコミュニケーションの大切さについて述べよ
◆演出家の意向を元に音を決める上で、コミュニケーションが取れないと、演出家の意向をきちんと反映できなくなる。また、平台を二人で運んだり、バトンの上げ降ろしする際に、声を掛け合わなかったら、平台を落としたり、降りてくるバトンに気づかなかったりして、事故に繋がる。
◆相手の立場や地位なども考慮して、上手に発言しなければならない。
◆会話がないと、信頼関係が生まれません。まずは会話をし、その人を知り、信頼関係を築いて仕事をする。そのために、コミュニケーションが大切になってくると思います。
◆演者や演出家など舞台に関わる人とコミュニケーションを取ることで、相手に安心してもらえるのみならず、連携が取りやすくなり、舞台をより良いものにできる。
◆スタッフ同士でコミュニケーションを取り合うことで、仕事を効率よく進めることができたり、演者とコミュニケーションを取ることで信頼関係を作ることにも繋がり、よりよいパフォーマンスをお客様に提供できたりするのでコミュニケーションは大切である。
◆意思疎通が難しくなれば、円滑に作業を進めることができず、演者にも迷惑がかかってしまう。それだけでなく、コミュニケーションが取れないことで、事故や怪我にも繋がりかねない。
◆自分の考えを伝えることは、相手の考えを知ることもできて、とても大切な手段であり、もっといい「仕事」にもつながる。
◆舞台スタッフとしてコミュニケーションは非常に重要である。なぜなら、デザイナーの思い描く形や、観客の楽しめる形、また演者の見せたい形などの抽象的な情報や、バトンの上げ下ろし時の見張り、入出力の確認の際のステージ担当と卓担当のコミュニケーションや他の分野のスタッフとの連絡など具体的な情報の伝達を円滑にすることで、よりよい本番に繋げることができるからである。
◆音響の仕込みひとつをとっても「自分が担当するところができればOK」ではなく、スタッフ同士が連携をとってより良い舞台・音楽にするためにも、コミュニケーションを取り合い、協力することが大切。
◆良いステージをつくるには、出演者や他のスタッフと意見や意思を共有し、同じ方向を向くために挨拶から始まりしっかりとコミュニケーションをとることが必要。
◆舞台のスタッフとして、プロデューサーや演出家など、外部の方とのコミュニケーションはもちろんのこと、舞台スタッフ同士のコミュニケーションも大切だと実感しました。どのバトンを下ろすか、どのマイクで喋っているか、など、常に意思疎通をはかることができるように、日頃からコミュニケーションの取りやすい雰囲気や環境づくりが大事だと考えています。
◆舞台、エンターテインメントの仕事は様々な立場の人が集まってできている。会社も違えば役割も違う人たちが、それぞれの立場での意見の違いで、時にぶつけあうこともあるが、最終的にどこに着地させるかを明確にして、全員で公演成功まで同じ方向を向く努力をしなければいけないと思う。
◆相手によって使い分けて、うまく伝えることを心がける。礼儀・仁義・恩義を重んじ、技術スタッフとしての作法を充実させる。
◆舞台芸術は全てのスタッフが意思疎通を図り協力して作り上げるものである。そのためには信頼関係を築くコミュニケーションが不可欠で、以下に述べる点などに気を配ることが大切である。・相手の立場や地位なども考慮して上手に発言する。・挨拶をはじめとした礼儀や仁義、恩義(お礼の心)を重んじる。・できるだけ多くの方々と謙虚な態度で接する。
◆観客に感動を与える舞台をつくるためには、スタッフ全員がお互いに邪魔をせず協力していく必要である。そのためには独りよがりではなく、コミュニケーションを取りながら最善を探っていくことが求められる。また舞台では重い機材や高所での作業など危険を伴うことも多いため、安全を確保する面でもお互いのコミュニケーションが大切である。
◆舞台のスタッフは、全員足並みを揃えて、出演者とともに、観客を楽しませ感動させ、演者の思いやイベントの思いなどを伝えるために、コミュニケーションが大切である。相手に内容を伝えることだけでなく、自分の言いたいことを理解・納得していただくために、相手の立場や地位なども考慮して、上手に発言することが大切である。挨拶などの礼儀、約束事を守るなどの仁義、教えていただいたことに感謝する心などの恩義を重んじて、先輩など多くの人と交流をもち、何をinputし、何をoutputするかよく考えながら、コミュニケーション術を身につけていくことが大切である。
◆コミュニケーション能力がないと作品においてはそれぞれのプライド等が優先してしまい偏ったものしかできない。作業においても意思疎通ができないことで非効率になったり、ときには危険が伴ったりする。作品を作り上げるに様々な人が携わり、十人十色な考え方が存在することを理解することで、まずは相手のことを気遣い、相手の考えを尊重することが大切である。
◆出演者や他のスタッフなど、公演に関わるすべての人とコミュニケーションをとることによって、観客に伝えたいことや演出の意図などをお互いに理解することができ、より良い作品をつくることができる。
Q この講座で学べたことを述べよ
●知っていることは改めて初心に帰って再確認することができ、知らないことは講義や実技を通して一から学ぶことができました。他にも音響だけでなく、照明やコミュニケーションなど、他の項目についても理解し、舞台に関わる上で大切なことを、1日を通して学ぶことができました。
●普段は、音響のことを専門に学習をしているが裏方として携わる大道具や照明の基本知識を学べたことで、互いに効率よく仕事をするためにはどうしたら良いかなど、周りへの視野が広がった。また忘れていた音響の基本的なことも復習ができ、機器の扱い方などの流れを再度勉強できたことで初心に振り返ることができた。
●主催者、出演者、観客の三者から満足していただくために、スタッフはいつでも手を抜かず自分の能力を十分に生かすことに努めることの大切さを学びました。そのために、初心を忘れない、協同する、安全にする、邪魔をしないなど、注意すべき細かい点をたくさん教えていただきました。これからの活動では、出演者がより良いパフォーマンスをできるように、そして観客が喜び感動してくれるように、今回学んだことを生かし、常に新しい好奇心をもって、音や環境をしっかり整えていきたいと思います。小学校教員を定年退職して、今回の講座で学びましたが、現役中にもっと早く学んでおけば学校現場で役立てることができただろうと思いました。
●音響に関して素人ながら、講師の方々のご指導により基本的なマイクのセッティングの方法、8の字巻き、調整卓の使い方、舞台配置などを学べました。また音響の仕事内容だけでなく、音響の方々がどういった思いで舞台に関わっているかをプロの方から聞けたのは、私にとって大きな学びとなりました。今後自分の仕事に、この経験をいかしたいと考えています。
● 多くのことを学びましたが、テキストの内容以外で特に心に残っていることを数点述べさせていただきます。
・講師の方々の熱い想いをもとにした講義を体験することができ、いつまでも初心を忘れず、さまざまな事柄の違いに対応して改善していく姿勢のお手本を見ました。
・受講者の質問や自己紹介から、一つでも多くのことを学んで各自の現在の活動や将来の仕事に生かそうとする姿に敬服しました。
・山台の組み方、ステージ上の配置方法、PA卓結線、調整卓の操作を基礎から実習させていただきました。その際に、受講生同士で役割分担をするコミュニケーション力を育成するように配慮があり、責任を持って取り組んで達成する喜びや満足感も味わわせていただきました。
●普段は直接担当していない舞台技術のことを実体験することができ、たいへん有意義な時間を過ごせました。今回の講座で学んだことを踏まえ、各公演における品質向上、さらには施設リニューアルに向け、出演者や舞台技術者の満足度を少しでも上げられる施設設計を目指していきたいと考えております。
●舞台技術に関して現場では、今更聞けないことや、分かっているつもりになっていたことが多く、初歩的なところから学び直しができた。質問にも丁寧に答えていただき、また他の受講者の質問を聞くことも非常に参考になった。普段、乗り込みの舞台スタッフを受け入れる立場の小屋付き・主催側スタッフとして、学んだ知識を活かし、舞台スタッフ・制作スタッフ・アーティストのコミュニケーションの橋渡しとなれるよう努めたいと思う。技術的なことの学びとしては、「8の字巻き」も今までなんとなくやってきたが、もっと早くなる方法に矯正していただきありがたかったです。また普段は小さな音楽堂で働いているので大きなホールを使っての仕込みバラシは非常に刺激的だった。今後も向上心を持って、音響家協会主催の講座に参加していきたい。
●これまでずっとバンド等で演者側の経験があり、先月から初めて裏方の仕事に携わっている者です。舞台のことは知っているつもりだったのですが、いざ経験してみると知らないことが多すぎて、今回の講座でも大変勉強になりました。「舞台まわりを客席から綺麗に見せる」という意識が自分の中にあまりなかったことがわかったので、ステージ上でのケーブルの配置の方法や毛氈の掛け方など、この講座で学んだことを活かし、今後に役立てたいです。
●機材の扱い方、ステージの設営について何気なくやっていましたが、もっと気を配れることがあると気付きました。プロの方々のお話はとても勉強になりました。
●日頃は音響の側ではなくミュージシャンという音響さんのお陰で音を出せている立場なので、舞台を裏から支えていく基本の考え方、その考え方のもと基礎技術の応用、実際の仕込みでの動きなどを肌で学べた素晴らしい機会でした。演者も音響さんも、観客に対して「良いものを創り届ける」という同じ目標のもと、高みを目指す同志であることを理解できました。
●実際の現場での、用語などの知識やリスク管理、職業倫理の様子を知ることができ、とても有意義な時間を過ごすことができた。また、これまで独学でやってきたため我流でやっていた部分や疑問点を即座に先達の皆様に聞くことのできたのは、音響や舞台の勉強を進めていく上で非常にありがたいと感じた。
●実際に舞台に上がって、実習をさせていただきとても楽しかったです。実習中も分からないことがあればすぐに教えていただけたので、とても心強く、積極的に実習に参加することができました。音響機器の繋ぎ方では、今までしっかりと理解できていなかった部分も講義や実践を通じて理解することができとても嬉しかったです。
●8の字巻きの効率の良いやり方、仕込み図の見方、卓とマルチボックス間の接続などを新しく学び、今までに得た知識を再確認することもできた。
●舞台の音響について勉強した中で、演者のやり方や、お客さんへの見え方を考慮してケーブルなど機材を置き、セッティングを行う。これを聞いて改めて自分はまだまだ想像力に乏しいと思いました。常に音のことだけではなく、見え方も想像して仕事をしていきたいと思いました。
●演劇をやっていてなんとなくやっていたことを論理的に身につけることができ、新しい知識を得ることができた。特に仕込み図の見方は、これから先、演劇をする上で重要になる知識であり、実際にやってみることで実感を持って身につけることができた。
●私は舞台に関しては完全な素人であり、今日の講座を受けるまでどんな事をしているかざっくばらんにしか知りませんでした。しかし、講座を受講し裏方担当の方々がどのような作業をしているか知ることができ、とても勉強になりました。今後の業務においては、舞台担当の職員と密接にコミュニーケーションをとり、積極的に協力していこうと思います。
●私は高校の演劇部で音響をしていました。高校演劇の音響の仕事は、SEなどをパソコンで編集することと、本番のオペレーションですが、スピーカの設置、音響卓の設営などは今までやったことが無く、新鮮な経験となりました。
●普段は音響をお願いして歌う立場なのですが、今回ひとつひとつ丁寧に勉強したことで、チームとしていいものを作り上げていきたいと思う気持ちが強くなったと思います。たくさんのみなさんと関わることができて、ほんとに刺激的な時間でした。
音響家技能認定講座・ベーシックコース オンライン実施報告
実施日:2022年2月7日〜8日
配信会場:東京・調布市 ティーラウンジ FUSHA
この講座で学べたこと(受講者感想)
●日頃演者の立場で音響に関わる中で、マイクロホンの指向性の種類を学べたことが活動のプラスになりました。近接効果などの音色の変化をマイクワークとして取り入れた歌唱などあらためて活用していきたいと思います。日常なにげなく感じていた音の世界が、具体的にみえ、理論で学んだ音に対して愛着を感じもっと学んでみたいと思いました。
●音響の仕事について、数年が経ちましたが、普段なかなか専門的な知識等を学ぶことができず、この度は良い機会となりました。また、コロナ禍のためオンラインにて受講できましたことに、大変感謝しております。
●音響の基本から、すぐにでも活かせる基礎知識を学べてとても貴重な時間を過ごせました。特にマイクロホンの講習はとても勉強になるお話を伺うことができました。
●音響システムの基礎的な知識についてとても良い勉強となった。特に、一昔前の機材やオペレート方法や周波数・デシベルの違いによる音の違いを体感できたのは面白さもありよい経験となった。また、音響の仕事がさまざまな気遣いや苦労の上に成り立つことを再認識させていただいた。
●基礎の確認、技術の応用や知識の拡大ができ、計算などでできる音を理論に基づき改めて正しい音の理解ができました。
● 今更聞けない音響の基本から、すぐにでも活用できる基礎知識を学ぶことができ、とても貴重な時間を過ごせました。特に、マイクロホンの講座では勉強になるお話をたくさん伺うことができました。
●今まで「なんとなく、感覚で」行っていた音響操作に関して、歴史や仕組みを知り、知識として頭で理解することで、より確実な、左脳的なオペレーションを行えるようになれると感じたし、それが大切なことであるということが学べた。
●歳を重ねた今、基礎を再度確認できた。お恥ずかしい話、知らない用語もあったので学べて良かった。学生の頃こんな教科書に出会えれば良かったー!後輩への教え方のヒントも学べた。初心忘るべからずで、明日から心機一転して頑張ろうと思えた講座だった。
●舞台音響全般の基本を学ぶことができた。特にスピーカーシステムや、音の性質、台本の読み方・書き方、マイクの指向性の原理など、改めて舞台音響の基本を学び、わかっていたつもりだったことや、あやふやだった部分をしっかりと学ぶことができて、自信に繋がった。
●音響の仕事や機材、音やノイズについて基本的なことを学べた。
●dBの感覚をしっかり身につけたいと感じました。機材をうまく使うには安全に正しい使い方をしっかり学ばなければいけないので自社機材も再度見直そうと思いました。
●マイクやスピーカ、電源関係等々普段から携わっていて仕様、特性などもそれなりに理解していると思っていたものが講習を受けたことによって、改めて知ったことや勘違いしていた部分、曖昧だった部分といったものに気付くことができた。
●教科書を読むだけでは理解しづらかったことを、実際に比較した音を聞いたり、実演を見ることによって、分かりやすく学べました。
●ノイズとアースの章は大変勉強となりました。またパワーアンプの仕様の意味などわかっていなかった部分を学ぶことができました。
●現場で何となく感覚で行っていた作業が、講座を受講したことにより少し理論的に考えられるようになったと思います。音源とスピーカの位置による時間差の補正の計算方法など実際に現場で使用していきたいと思いました。今まで音響の基礎をしっかり学ぶことがなかったのでとてもいい機会になりました。
●舞台、芸能の起源的な部分。音響理論の基礎的な部分。電池が温度により効率が変化することなど、あげればきりがないですが、勉強させていただきました。ありがとうございました。
●今まで何となく分かっていたつもりの物がしっかりと原理から理解でき、音響の基本から仕事まですぐにでも活かせそうな実践的な知識を得ることができました。
●しっかりと分かったうえで現場に出ることができるような基礎的な内容を学ぶことができました。
1級サウンドシステムチューナ認定試験実施報告
日時:2021年12月3日(金)または5日(日)14時〜16時 オンラインで実施
『サウンド システム チューナは、ホール音響設備やコンサート音響システムを正しく接続・設置して、電気音響特性とホール音響特性を整合させ、音響機器の性能を十分に発揮させるための音場補正をする職業で、音響装置の総合的な整備士です。
この講座は、測定装置の操作方法を学ぶものではなく、スピーカシステムを適正に設置することと、有効なチューニングポイントを見極める技を指導するものです。』
ビギナーズコース兵庫実施報告
日 時:2021 年2月26 日
会 場:兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール
主 催:一般社団法人日本音響家協会
主 管:日本音響家協会・西日本支部
共 催:兵庫県立芸術文化センター
協 力:全国公立文化施設協会近畿支部
◎「この講座で何を学べたか?」の設問に対する解答
- 頭で理解していても、いざ行動するとなかなか動けなかった。ただ、これまでに持っていた知識の再確認、向上ができたと感じる。実践する事が大切だと感じた。からだで覚えて自分のスキルにしていこうと思います。
- 周りに如何に見て、気を配らなければならないのか、舞台における音響、ホールの大切さを実感した。普段からもう少し視野を広げて見ようと思った。
- 今回の講座で普段現場に入ってやっている事の奥深さを知ることができました。ブームマイクスタンド1つとってもさまざまな使い方や気をつけるべき点がたくさんあることに気がつきました。基本であり、できて当たり前だと思っていたことも、私はまだその全てを知ってはいないと思い反省したいと思います。普段、音響しかやらない私にとって照明のことや平台を組んだり毛氈を扱ったりすることはとても貴重な時間でした。また、人との繋がりの大事さや現場での態度や振る舞い方など講師の方々を見て学ぶべき所だなと感じました。今後の現場でも今回で学んだことを発揮できるように日々精進したいと思います。
- 日常的にホールのイベントに小屋付きとして携わっているが、舞台人としての心構えや技術的なことの再確認ができました。狭いコミュニティの中で培った自分たちの知識や技術がガラパゴス化してないか不安があったため、本講座はとても為になりました。常に初心を忘れずに、という言葉が一番心に残りました。
- 音響は複雑な仕込みやオペレーションなど、体を使ったり耳で聞いたりと、コンピュータなどではなく一から人の手によって成り立っているものであることを学びました。また、舞台用語や鉄管巻き、8の字巻き等の巻き方、毛氈の畳み方など、昔からの経験の中で分かりやすいように、やりやすいように変容していくものであり、形式的なものではないということも学びました。
- ひとつの舞台を作り上げるためには、知識のある人材が協力し合うことが必要であること。小さなミスが、出演者の演技や演奏を台無しにしてしまうこと。
- すべてのことは、人付き合いから成り立っているもの。芸能は人をリードし、人を教育する面もあるのですが、それだけに偏ってはいけないということ、あくまで音楽という音を楽しむ(楽しんでいただく)というスタンスの上に客商売があることを忘れてはならないと再認識しました。
- 音響に関する仕事だけでなく、舞台に関わる他の仕事のことも理解することができました。多くの人が関わって、素敵な舞台を作り上げているということを改めて学べました。
- 私は普段舞台の方でアルバイトをしているのですが、実際舞台に登った際は照明であったり、映像であったり、道具のこともすることがあります。学校の授業では平台は組まないですし、照明には触れることもありません。今回の講座で正しく1から教えて頂けたので、なぜそうするのかや、気をつける点などの知識が増え、さらに安全に丁寧に舞台をつくりあげる技術を身につけることができました。サービスの心を大切にしながら舞台に関わる色々な方とのコミュニケーションも含めて努めて行きたいと思います。
- 実際の舞台で演習をおこなうことで、座学では体感できないさまざまな現場での動きや基礎の素養が学べた。また、舞台の構造や台組なども実際そこにあるものを見ながら学習することで理解が深まった。
- 音響のセッティングは最後、撤収は最初ということを知り、他職種の業務を把握したり周りをよく見て判断したりすることの重要性をより感じ、スピーディーに行動しなければならないと思った。技術面では実際にマイク、スピーカーのセッティングをさせていただき、その時の観客からは見えない気遣いなど隠された配慮が多く、また調整卓では操作するつまみやボタンが多く、より心地いい音とはなにか考えさせられることもあった。これまで、イメージとして裏方はコミュニケーションが苦手そうだと思っていたが、そうではなく1つのものを作り上げて伝えるのには必要不可欠であり、コミュニケーションの重要性を学んだ。貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。この講習を受けることができて、本当によかったです。
- PAの本当の役割、仕事、舞台側の人の役割、仕事がわかった
- これまではみよう見まねで何となくであったが、このセミナーで音響の基本を理解し、身につけることができた。特に設営やバラシなどはこれまで関わったことが無かったので、今後は積極的に機会を掴み技術向上につなげます。
- 舞台・音響・照明の基礎知識だけでなく、舞台の裏方として何を重んじるべきか、そのために必要な基本的な知識・技術はどういったことか、を経験豊富な講師の方々から直に学べました。素晴らしい時間と機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。
ベーシックコース/オンライン実施《文化庁助成・文化芸術活動継続支援事業》
日時: 2021 年1 月26 日(火) ~27 日(水) 13:00〜17:30
講師:糸日谷智孝、井戸覚道、奥山竜太、平井秀昌、高崎利成
ネット配信技術:平井秀昌、高崎利成
コーディネータ:八板賢二郎
統括:高崎利成
協力:株式会社エヌエスイー
主催:一般社団法人日本音響家協会
◎「この講座で学べたことは?」の設問に対する解答
- 今まで感覚的に知っていたことや「こうやるもの」と教わってきたことが、今回体系的に学び直すことができた。音響家としての実務能力向上に役立った。
- マイクやスピーカー、パワーアンプ等機材の実際の仕組みに基づいた運用方法、音響の基礎を改めて確認し、学ぶことができました。実体験を元にした話はイメージもしやすくとても参考になりました。実演も分かりやすく丁寧にしていただきありがとうございました。
- 入力から出力系の機器の性質、特徴を詳しく学ぶだけでなく物理学的な側面から、より科学的な理解が深まった。特に位相に関する知識や、客席での音の遅延時間の計算方法など今後、具体的に応用できることが学べた。
- お恥ずかしい話、忘れかけていた音響の基本知識を再確認できました。実演を交えていただけたので、わかりやすかったです。今後のセミナーも有料配信していただけると、勉強の機会が増えて嬉しいと思います。
- プロの音響は、「伝えたいことを正確に伝えること」という基本を再認識させられました。
- 舞台芸能の起源から音響調整卓まで音響技術の基礎を学ぶことができて大変よかった。また普段感覚で作業していることが多い、音の性質や聴覚心理現象などの物理的な仕組みを学ぶことができ、大変勉強となった。
- 普段仕事で音響をしていると、ある程度はルーチンワークになってしまい、より良い音について考えることが少なくなっています。今回の講習を受けて、音響について知らないことや考えることが本当にたくさんあるということを改めて実感しました。自分に仕事においても、さらに突き詰めて、より良い音響について考え続けることができればと思いました。
- 普段、何気なく理解はしているものの、感覚的に理解していることが多いため、理論的に説明いただき明確になった面と、より複雑にとらえてしまった面とありましたが、今さら聞けない分野など多くあり、とても為になりました。
- 今まであまり気にしていなかった、芸能の起源や劇場での仕事の心得を再確認でき大変ためになった。「ごみ鎮め部分の音量が小さいからといって、大きくする必要はない」という言葉は、なるほどと感じた。マイクの性質やスピーカの配置、アースの取り方など今まで意識していなかった部分も学べて、大変ためになった。
- 普段音響業務にあたる中で、当たり前だと思っていたことや、さほど気にしていなかったことを、改めて確認することができました。
- 音響照明の専門学校を卒業していますが、インピーダンスがいまいち理解できていませんでした。この講座を通して改めて理解できて本当に助かりました。
- 普段の業務で何となく手順を教えられたとおりに繰り返していたことに、明確な理由付けができました。
- 単一指向性のマイクが全指向性と双指向性の組み合わせで成り立っていることや、それぞれの指向性の感度以外の違い(風および振動雑音の影響の受けやすさや近接効果のかかり方)については初めて知った知識だったので、今後のマイキング時の考え方に活かせると思いました。
- 実務で行っていて当たり前のことはわかっているが曖昧だったことなど、基礎の部分をおさらいでき、改めて理解を深めることができました。また、音響とは何かの起源、普段何気なく使用している機材などの扱い方や基礎知識を再確認することができました。
- 芸能の起源や舞台の種類、マイクの構造やスピーカーの働きなど基礎に立ち返り、学び直すことができました。また、現場で得た知識を深く掘り下げて学べました。
- 今までの現場での再確認や、もっと奥深いことを学べ、今回講座を受講して良かったと思います。芸能の歴史的なことも知れ、今後も音響だけでなく、舞台や照明も学んでいきたい。
- 普段行っている業務の音響セッティングや調整、また機材選定などに関して、改めて基本的な理論や概念などを学べ、自身の知識を見直すことができた。今後は今回の講座内容を生かし、普段の行動を見直しながら、よりプロとしての業務にあたっていきたいと考える。
- マイク~パワーアンプ~スピーカで、どのような物理現象が生じていて、それがどのように感じられているか、それをどのように使うかについての知識を学べて理解が深まった。
- 普段、感覚的に行なっていることを、文章でしっかり確認できたことと、理論的に解釈することができた。また、自分の好きな分野と、苦手な分野で、知識の差があったことを改めて認識した。そして、音響家としての必要な心構えなどもチームに教えたいと思います。
- これまで分かったフリをしていただけだと、気がつきました。またデシベルなどについても勉強できて良かったです。
- 今までは雰囲気で考えていた音響の仕組みを論理的に考えることができました。マイクの特性の実演がわかりやすかったです。物理や機械的なことは完全に理解できませんでしたが、テキストを参考に、今後に活かしていきたいです。このような時期にオンラインで受講できたことも助かりました。
- 昨年は3級を受講しましたが、今回はより専門的な知識を学ぶことができました。
- アースや音の性質など、感覚的に把握していたことを、文章として改めて理解できたこと。
- 音響家としての基礎から、ディレイを割り出す計算方法や、出力音圧レベルの計算方法など、これから仕事をしていく上で必要な知識や技術を学ばせていただきました。特に位相干渉の問題についてちゃんと考えなければならないと思いました。
- 技術的なことはもちろんですが、ただ音を聴衆に伝達するのではなく、舞台上に立つ演者さんだったり、演出家さんの意図を組んだりして、音楽や演出に込められた思いを見ている人に正確に届けることが舞台を作る上で大事であることなど、音響に携わる人間として必要な基本の心構えを改めて学ばせていただきました。
- 私は普通の大学を卒業後、一般企業を経て音響という仕事に就いたため、座学をきちんと学ぶことなく現場経験でなんとなくわかったつもり(感覚)でここまで来ていました。このような講座を受けることで、改めて「きちんとした正しい知識を持つことが大切だ」ということが理解できました。ホールの常駐スタッフをしているため、アースなど意識することも少なかったので、これからもっと理解を深めないといけないと思いました。また、この講座を学ぶために予習してわからなかったことなども実際に講義を受けることで理解できたので、これからも学び続けることが大切だと学びました。
- 初心に帰った気持ちで、二日間学ぶことができました。特にノイズの種類においては、今後、ノイズの原因を特定するのに、大変勉強になりました。
- 普段、何気なく行っている業務がどのような意味をもっているのかを改めて知ることができました。ケーブルの引き回しなどでは、足りなければ一本足せばいいや、となることが今まであったのですが、長いケーブルで引き直すひと手間を惜しんではいけないと思いました。
- 音響技術の基礎の復習や、細かい計算式を知ることができました。今後の業務で生かしていきたいと思いました。
- 音の特性が様々あり、音を出す場所によって気を付けなければならないことがあるということを学べた。音を出すのにあたって、観客にどのように聞こいているかを想定しなければならなく、また、それは細かい計算によって導かれている。
- 改めて、勉強になりました。講師の方々が教科書を分り易く解説して下さって頭に入り易かったです。
- 今まで曖昧に行っていた部分があったのだと感じました。今後、音響の仕事に携わる者として、さらに理解を深めていかなくてはと感じる二日間でした。
- 音響家として基本であり、かつ重要なことを学ぶことができて貴重な経験をすることができました。今回学んだことを、繰り返し頭に叩き込んで基本をしっかり勉強していきたいと思いました。
- 普段はホテル音響をやっておりますが、コンサート等や演劇等の大規模の音響システムに携わって行きたいと思い、受講させていただきました。普段何気なくやっていた仕込みや調整について、詳しく学ぶことができました。特に音響は目に見えない部分でのトラブルが多いため、照明や映像よりも深い知識が必要だなと痛感致しました。特に聴覚心理についてはモヤッとした知識しかなかったため、ハッキリとした知識を得ることができました。今回の受講で得た知識を生かし、お客様に良い音楽を届けられるように邁進したいと思います。
- 音響に関わるものとして、音の基本的な性質、原理、特性、およびそれらに付随した機器の取り扱いを学びました。また、同時に音響家としての現場での所作や、演劇や音楽の上演を円滑に進めるための心得と姿勢についても学べました。このような貴重な機会をご用意いただき心より感謝申し上げます。
- 現場でも学べない基礎中の基礎を学ぶことができた。基礎であっても知識がなく活動していたので、いい機会を与えて下さり感謝しております。
サウンド システム チューナコース/オンライン実施《文化庁助成・文化芸術活動継続支援事業》
日 時:2020 年10 月20 日(火)13:00 ~ 15:30
講 師:井戸覚道、奥山竜太
ネット配信技術:平井秀昌
コーディネータ:八板賢二郎
協力:合同会社エーアイプロダクション、株式会社エヌエスイー
主催:一般社団法人日本音響家協会

◎受講者への設問「受講して学べたこと?」への解答
- 自身がこれまで感覚と経験のみに頼っていた行動を確かな知識によって裏付け、否定された点
- 専門用語とチューニングの流れ
- サウンドエンジニアの仕事はサイエンスであり、誰が行っても同一の結果が得られなければならない、という考えは非常に勉強になりました。オペレーターとサウンドエンジニアでは担当する分野その物が違うとういことを肝に銘じ、独り善がりにならない調整を心がけたいと思います。
- まずシステムチューニングは「サイエンス」であり誰が行っても同一結果にならなければならない事、またEQで補正する以前にスピーカ配置を含めたサウンドシステム設計が重要である事、チューニングの測定および補正の手法を学ぶ事ができました。
- 「サイエンス」ということで正確に動作するように知識を持ち調整することが大事。
- 機器選定の基本として、レベルダイヤグラムの考え方をしっかり計算し、最適化することの重要性を再確認した。
- イコライザーで補正できる要因とできない項目の見極め方
- 位相に関して何となく理解していた部分ですが、今回の受講でより理解することが出来ました。
- システムチューニングの基本的な考え方と、そのポイント。そしてサイエンスであること。
- 改めてスピーカーの設置、環境条件、配置、測定、チューニングなどシステムを構築し、いかに最適な音場を作っていかなければいけないと再認識できた。今後の仕事に存分活かしていきたいです。
- 根本的な理論を学ぶ事で、柔軟な幅の広いデザイン、チューニング、的確な対応を理解する事が出来た。
- システムチューニングはサイエンスであり再現性が必要であること、そして、実際に人間の耳で聞き判断する必要があることがわかった
- チューニングの実作業がリアルに学べた。
- システムチューンは「サイエンス」「アート」ではない。誰が行っても結果が同じで、すべてを明確に言葉で説明ができる
- システムチューニングはサイエンスであり再現性が必要であること、そして、実際に人間の耳で聞き判断する必要があることがわかった
- 改めて、理論立ててシステムを理解することを学んだ
- 受講するまで、音楽は感性でなんとかなるものだと思っていました。しかし、システムエンジニアにおいては、起きている現象を科学的理論に理解し、測定値など定量的な解決策を考える必要があるということが分かりました。その上で、数値では把握できない音の脳内処理など、人間でしか調整できない部分を考慮する必要があるということも分かりました。システムエンジニアとオペレータ業務を兼務する際は特に、科学とアートの線引をしっかりと意識する重要さに気付かされました。この度は、貴重な情報・経験をさせていただき、誠にありがとうございました。
- 経験や慣れで対処していたことの根拠や理論が学べました。グラフ動画での位相についての説明や、後半の測定データの分析方法など、とても解りやすかったです。
ビギナーズコース・札幌 実施
日 時:2020年2月26日(水)
会 場:札幌サンプラザホール
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:日本音響家協会・北海道支部
ベーシックコース・東京 実施
実施日:2020年1月27日(月)~28日(火)
会 場:国立能楽堂2F・大講義室
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:日本音響家協会・東日本支部
ビギナーズコース・名古屋 実施
日時:2019年12月12日(木)
会場:名古屋市昭和文化小劇場
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:日本音響家協会・中部支部
ベーシックコース・大阪 実施
実施日:2019年9月2日(月)~3日(火)
会 場: NHK大阪ホール・リハーサル室(5F)
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:一般社団法人日本音響家協会西日本支部
協 力:NHK大阪ホール
後 援:公益社団法人全国公立文化施設協会近畿支部
サウンドシステムチューナコース・東京 実施
日時:2019 年4 月9 日(火)13:00 開始
会場:国立能楽堂大講義室
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:日本音響家協会 東日本支部
講座終了後の筆記試験「この講座で学べたこと」の出題への回答です。
■自分の不得手な箇所を再認識できた。測定ソフトの具体的な使用方法ばかりを憶えてしまうので、今回はその根源的な部分を学べてよかった。
■理論を学ぶことでチューニング箇所の判断が的確になることを学べた。これからも、理論と経験と、耳を鍛えて現場作業を行いたいと思う。
■様々な情報をもとに状況を判断して、適切なシステムデザインをすることが大切だと理解できた。
■フラットにチューニングするのがチューナの仕事、そのシステムを用いてアートの部分を担うのがサウンドエンジニアの仕事、という考え方を学びました。
■システムチューニングは「サイエンス」だと学びました。今後の仕事が楽しみです。
■今まで知り得なかった分析の知識とサイエンスの目、そして最後は人間の耳による判断が重要であることが理解できました。
■チューニングはサイエンスに特化すべきという意義を学べました。
■機器の配置、システムの正常な稼働、FFTによる周波数分析の順で音を確認して、最後は耳で聴いて確認することが重要であることを学べた。
■フラットにチューニングするのがチューナの仕事、そのシステムを用いてアートの部分を担うのがサウンドエンジニアの仕事、という考え方を学びました。
■チューニングの基本を確認でき、進むべき道が明確になりました。
■システムチューニングの基本を学べて、サイエンスとアートを切り離すという考え方に興味を抱きました。
■システムチューニングのイロハをしっかり学べました。何のために、何をするのかを理解できた。
■チューニングとミクシングを分けて考えることが理解できた。
■これまで理解していなかったこと、必要なことが明確になった。
■問題の対処、見極めのポイントなどを学べた。
■システムチューナとしての正しい思考とはなにかを学べた。
■RTAとGEQよりも深い手法について学ぶことができた。
ビギナーズコース・兵庫 開催
日時:2019年3月6日(水)10:00〜18:00
会場:兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:日本音響家協会・西日本支部
共催:兵庫県立芸術文化センター
クリエイティブコース神戸開催 実施
日 時:2019年2月4日(月)11:00〜18:00
会 場:神戸こくさいホール
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:日本音響家協会・西日本支部
協 力:株式会社神戸国際会館
ベーシックコース札幌開催 実施
日 時:2019年2月19日(火)~20日(水)
会 場:札幌サンプラザホール
共 催:一般社団法人日本音響家協会北海道支部
ベーシックコース東京開催 実施
日時:2019年1月28日(月)〜29日(火)
会場:国立能楽堂大講義室(国立能楽堂2階)
共 催:一般社団法人日本音響家協会東日本支部
ビギナーズコース名古屋開催 実施
日時:2018年12月6日
会場:名古屋市昭和文化小劇場
主催:一般社団法人日本音響家協会
共催:一般社団法人日本音響家協会中部支部
ベーシックコース大阪開催 実施
実施日:2018年9月3日〜4日
会 場: NHK大阪ホール・リハーサル室(5F)
主 催:一般社団法人日本音響家協会
共 催:一般社団法人日本音響家協会西日本支部
協 力:NHK大阪ホール
クリエイティブコースの模様
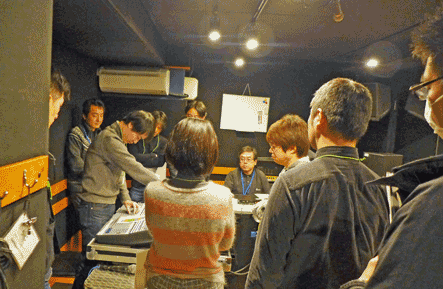



《受講者たちが、この講座で学べたこと 〜2018年1月23日開催〜》
1,講師のみなさまのアドバイスの的確さ。
2,ミックスのバランスについて、音をプラスするだけでなく、マイナスすることの重要性。
3,プロの方々の技を目の前で見ることができて教えられました。本で読むのと、目の前で見るのとは大違いでした。
4,音量を下げてミックスするとことで、音の輪郭がはっきりわかること。
5,音響家の担うべき役目・責務を改めて思い起こすことができた。
6,オペレーションするときの精神力と集中力が鍛えられた。演劇の効果音をオペレーションしてみて、さまざまな効果が生まれることを理解。
7,演劇の効果音は、フェーダの動かし方でさまざまな演出効果をもたらすことを学べた。オペレータは演技者として、俳優の演技をサポートできることを理解できた。ジャズミクシングでは、どのようにして的確なバランスをとっていくのかを学びました。演奏者が行っている音の駆け引きを最大限に観客に伝えられるよう、その音楽を理解して、素早い判断で的確なバランスを瞬時にとることの大切さを理解。
8,ジャズでは、低音を大きくし過ぎて他の楽器をマスキングしないようにすること。演劇では、効果音でセリフを邪魔しないようにすること。
ベーシックコースの模様


ビギナーズコースの模様


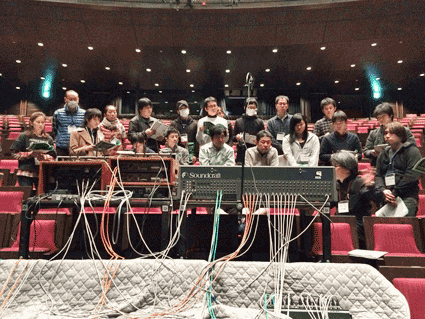
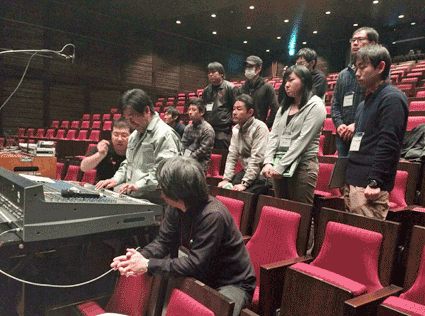
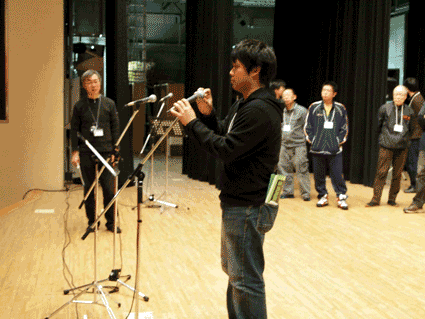


クリエイティブコース受講者資料(パスワードが必要)
